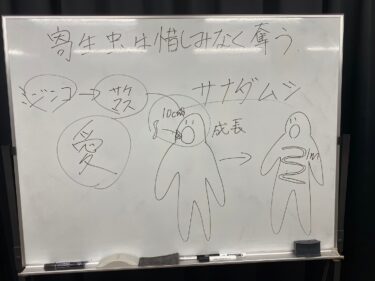まちだです。劇団words of hearts第18回公演「その生は受け入れがたし」を振り返っています。その第2弾です。
実際に稽古が始まったのは2月末。今回の公演でどんな作品にしたいのかを全員で共有し、戯曲を読み、作品のイメージを膨らませる作業を開始しました。初期の段階ではひたすら戯曲と向き合う時間を設けて、この絶妙な会話劇の構造を探りました。それは薄氷を積み上げるような繊細さが求められました。

進めていくと大きな壁が現れました。方言の問題です。物語の舞台が東北地方のとある町。5人いる登場人物のうち3人は東北地方(津軽地域と福島)出身。当然のことながら、この3人(プーチン、飛世、山木)にはその土地の方言で話すというミッションが課せられました。これだけでも難題なのですが、台本に書かれている台詞は標準語なのです(!)。当たり前ですが、これでは我々にはどうしようもありません。とりあえず上演許可を頂いた青年団にお願いしてDVDをお借りし、方言部分を書き起こして台本に反映させました。(写真・高橋克己)
この作業は若手演出助手チームのいちひめ、らいか、りん、りりかの多大なる尽力がありました。恐るべきスピードで方言バージョンの台本が出来上がっていきました。その間、僕がしたことといえば、四人の作業の邪魔をしないように差し入れをすることだけでした。本当に優秀な若手たちです。四人との出会いも奇跡と呼べるでしょう。また方言指導として宍戸隆子さんにお越し頂きました。俳優陣も慣れない方言に苦労しながらも懸命に取り組んでくれました。曰く、「一端、頭の中で標準語に変換してから言わなければならないから倍疲れる」とのこと。実際、脳の疲労が激しかったのでしょう、差し入れのお菓子の消費量が半端なく多かったです。そんな時間を重ねながら、徐々に稽古場が東北地方になっていきました。


3月の半ば頃から実際にシーン作りに着手しました。とは言え、この作品には激しい動きはほとんど(全く?)ありません。必要なのは相手との距離感です。実際に稽古をしてみて分かったことですが、近付いたり離れる理由が物語の見え方にかなり大きな影響を与えるのです。俳優陣が同じ場面で違う距離感を試しながら稽古を始めます。このとき、演出である僕は基本的には口をはさみません。僕の出番はもう少し先。とにかくここは俳優に任せて、この場でしか得られない「何か」が生まれてくるのを待つのです。それは僕の予想を上回るものであり、それは僕がイメージしていた枠を内側から押し破るようなものです。とにかく僕を想像の外へ連れて行ってほしい。稽古の初期段階はそんなことを考えながら演出席で事の成り行きを見守っています。ここ数年、僕が演出の立場で行っている創作方法です。(写真・高橋克己)
やがて俳優陣が徐々に変化していきます。自分の台詞や行動が自分のものになり、それが相互に絡み合うと、その場の空気がどんどんうごめいていくのです。徐々に俳優を通して内面にある偏見、差別、すれ違い、不信、震災の経験、夫婦、家族、生き方といったこの作品の核ともいえる部分が瑞々しく透けて見えてきました。誰もが課題と共に大きな手応えを実感し始めました。「これはとんでもない作品に取り組んでいる」、稽古期間に幾度となくみんなで交わした言葉です。(写真・高橋克己)


こうして糸を紡ぎ、解き、時には裁断するようにシーンを最後まで繋ぎました。方言も少しずつ慣れてきました。この時点で4月の初旬。ようやく僕の出番です。俳優陣が築いてくれた土台に僕なりの想いを載せていくのです。毎度のことなのですが、この土台がまた本当に素晴らしい。ふんわりとしていて、でも頑丈で、こちらの要求を的確に受け止めてくれる、正に最強の土台です。その後も皆で議論を重ね、建設的な試行錯誤を経て、チームとして目指すゴールに向かいました。いつも稽古場には濃密な時間が流れていました。(つづく)